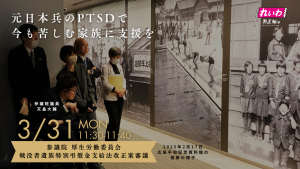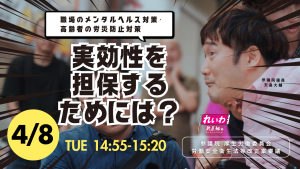2025年4月3日 厚生労働委員会質疑「テーマいろいろいきます 女子中高生の自殺増に向き合う/医療情報検索に障がい者の視点を」
〇天畠大輔君
れいわ新選組の天畠大輔です。私もまた本気で自殺したいと思った時期がありました。代読お願いします。
日本において、1年間に自殺した人の数は2003年、ピークを迎えました。3万4,427人でした。昨2024年は2万268人まで減少し、1978年の統計開始以来2番目に少ない水準となっています。この減少について政府はどう受け止めていますか、またその原因をどう分析していますか。
〇政府参考人(日原知己君)
お答えを申し上げます。令和6年の年間自殺者数でございますけれども、先月公表いたしました確定値におきまして、昭和53年の統計開始以降2番目に少ない2万320人となってございます。
その背景につきまして一概に申し上げることは難しゅうございますけれども、昨年は景気が緩やかに回復をし、雇用情勢にも改善の動きが見られたことなどが自殺者数の減少に影響を与えたというふうに考えてございます。加えて、平成18年に自殺対策基本法が成立しまして以来、国を挙げて進めてまいりました自殺総合対策が着実に成果を上げてきたことも言えるのではないかというふうに考えてございます。
ただ一方では、依然として年間自殺者数は2万人を超えておりますことや、近年の子どもの自殺者数の増加といった状況を踏まえまして、引き続き、関係省庁などとも連携をして、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、総合的な対策を推進してまいりたいと考えてございます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
〇天畠大輔君
とりわけ若者が自殺に追いやられています。代読お願いします。
10代における死亡原因の第1位が「自殺」なのは、G7の中では日本だけです。なぜですか。福岡大臣、お答えください。
〇国務大臣(福岡資麿君)
ご指摘のとおり、G7各国の10歳代の死因順位を見ますと、第1位が「自殺」であるのは日本のみであります一方、日本以外の国では不慮の事故が死因の第1位となることが多いということでございます。
WHOの手引きによりますと、「危険をもたらす状況は、大陸間や国々の間で異なるということにも留意しなければならない。隣国間でさえも文化的、政治的、そして経済的特徴が異なることがあるからである」とされておりますが、この10歳代の死因順位といたしまして自殺が日本で高くなっている理由を一概に述べることは困難であると考えています。
〇天畠大輔君
代読いたします。ほとんどの年代、属性において自殺した人の数が減少する中、2023年から2024年の1年間で「女子中学生」は80人から99人へ24%増加しました。また「定時制・通信制の女子高生」は66人から81人へ23%増加、2022年からの2年間で見ると47人から81人へ72%も増加しています。悲惨この上ない事実です。
このことを政府はどう受け止めていますか。また、その原因分析と対応について、厚労省、こども家庭庁の順にお答えください。
〇政府参考人(日原知己君)
お答え申し上げます。女子中高生の自殺者数につきましては、2020年以降増加をしておりまして、極めて深刻な状況であるというふうに考えてございます。自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しておりまして、様々な要因が連鎖する中で起きていることに留意が必要でございます。
そうした中で、警察庁の自殺統計原票データから把握できたもので申し上げますと、令和5年から6年にかけて最も増加した原因・動機、これを最も詳しい分類で見たものになりますけれども、女子中学生につきましては、「病気の悩み、・影響」のうち「その他の精神疾患」、これが13件の増加となってございます。定時制・通信制の女子高生では、「病気の悩み・影響」のうち「うつ病」、これが14件の増となってございまして、いずれも健康問題が増加してございます。
厚生労働省におきましては、若い方々が少しでも相談しやすくということで、子ども、若者の利用が多いSNSの相談につきまして、民間団体及び地方公共団体双方の相談体制の拡充や相談窓口の周知、また、地方公共団体や関係機関において自殺防止の支援に取り組まれる支援者の方の支援を行うことが重要と考えてございまして、都道府県等に他職種の専門家で構成されます「こども・若者の自殺危機対応チーム」の設置を推進するなどの取り組みを進めていくこととしてございます。
〇政府参考人(水田功君)
お答え申し上げます。議員ご指摘の女子中高生の自殺者数は、2020年以降増加しており「こどもまんなか社会」の実現を掲げるこども家庭庁として重く受け止めているところでございます。
こども家庭庁では、令和5年6月に取りまとめた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づきまして、警察や学校等の関係機関が保有する関連資料などを集約し、要因分析を行う多角的な調査研究、都道府県等における自殺防止支援者の支援を行う「こども・若者の自殺危機対応チーム」の設置の推進等に取り組んでいるところでございます。
また、令和6年版自殺対策白書において、令和4年以降の自殺者数のうち「自殺未遂後1年以内に自殺した者」は未遂歴がある自殺者数の過半数を占めることが明らかとなり、未遂者への支援強化が重要であることから、今後、自殺未遂者とその家庭を保健、医療、福祉、教育の各機関が連携して地域で包括的に支援する体制の構築に向け、新たに調査研究を行うこととしております。
このほか、子どもの自殺対策の効果的な周知と実効性のある自殺予防に向けまして、対象者に応じた広報啓発としまして、高校生を対象に、友人に悩みを打ち明けられた際のコミュニケーション方法を学ぶワークショップ等に取り組んでおります。
こども家庭庁におきましては、関係省庁と連携し、今後も、プランの各施策の実施状況を検証しながら、子どもが自ら命を絶つことのない社会の実現に向けて政府一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。
〇天畠大輔君
代読いたします。女性差別、学歴差別が若い女性を自殺に追い込んでいるのではないですか。内閣府、お願いいたします。
〇政府参考人(小八木大成君)
お答え申し上げます。令和6年の子どもの自殺者数、特に女性の中高生の自殺者数が令和5年と比べて増加したことは重く受け止める必要があると考えております。
子どもの自殺は、その原因・動機が不詳である場合が多いものでございますが、委員ご指摘のとおり、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しておりまして、様々な要因が連鎖する中で起きているものと認識してございます。
第5次男女共同参画基本計画におきましては、女性が社会的困難を抱えている場合、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に更に複合的な困難を抱えることがあるため、男女共同参画の視点に立ち、多様な困難を抱える女性等に対するきめ細やかな支援を行うことにより、女性が安心して暮らせるための環境整備を進めることとしております。
引き続き「固定的な性別役割分担意識の解消」に向けた意識啓発を含め、多様な困難を抱える女性に対する取り組み等の関連施策を推進してまいりたいと思います。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
自殺を思いとどまったからこそ、私はここで質問しています。相談しやすい社会にするにはどうしたらいいですか。通告なしですが、こども家庭庁からお答えください。
〇政府参考人(水田功君)
お答え申し上げます。すべての子どもが、子ども、若者が安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや体験などを、体験活動等に接する中で、多くの大人あるいは子どもたち、そういった方たちと接しながらできる場所、そういった場所を確保していくということが相談しやすい環境の中で重要かと思っておりまして、今後とも各自治体とも連携しながら、そういった取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。
〇天畠大輔君
相談支援体制にもっとお金を付けてください。代読お願いします。
差別や貧困、病気や将来不安などが様々な形となって人々を自殺へと追いやります。
「あたし中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字はとがりながらふるえている」
学歴差別と女性差別に苦しむ女子のラジオ番組への投書です。このような生きづらさや絶望を政治の側が取り除かない限り自殺はなくなりません。死ぬことではなく生きる方向へ、希望の方向へと続く道筋を具体的政策で示すべきです。
次に行きます。2023年通常国会で成立した全世代型社会保障法案の審議で、私は、医療情報ネットの「ナビイ」を通して国民に提供される医療情報の中に「入院時の介助者の付添いの可否」を入れるよう求めました。
2024年8月22日の第4回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会で、厚労省から「家族・介助者の付添い・同行」を医療機関からの報告項目に加えることを提案し、その方針が決まったことは歓迎したいと思います。ただ、同行・付添いに家族と障がい者の介助者が並んでいることに懸念があります。小児科病棟への親御さんの付添いから、重度障がい者の介助者まで含むとなると、それぞれ必要な体制は違います。明確にするために伺います。
平成28年厚労省発出の事務連絡「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」では、その人のコミュニケーション支援を熟知する介助者が入院中に付き添えること、また、重度訪問介護であれば入院中の介助にも利用できることなどを定めています。「家族・介助者の付添い・同行」ができると報告した医療機関は、この事務連絡に沿った受入れ体制を整えていると理解してよいのでしょうか。厚労省、お願いいたします。
〇政府参考人(森光敬子君)
お答え申し上げます。医療情報ネット「ナビイ」における医療機関が報告、入力する項目については、当事者団体の方にも参加いただきながら、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会において、幅広く障がいに関する項目の追加についても議論をしたところでございます。令和6年8月の取りまとめにおいては、委員お尋ねの入院中の「家族・介助者の付添い・同行」の可否についても項目を追加することとされ、現在、システム改修などの具体的な準備を進めているところであります。
この項目につきましては、入院中の付添いの対象などは子どもや障がい者についても様々な方がいらっしゃるため、ご指摘のような「特別なコミュニケーションの支援が必要な場合の対応」の可否にかかわらず、広く対応の可否を報告いただくこととしておりますけれども、特記事項を記載できる項目を設けておりまして、その中で特別なコミュニケーションできる介助者を入院に付き添わせることの体制を整えている旨を記載できるようにしております。
さらに、今回の報告項目の見直しに当たりましては、併せて障がい者及びその家族向けの相談窓口の有無についても報告を求めることとしておりまして、障がい者である患者の方が医療機関に更に具体的な相談ができるように活用いただきたいと考えておるところでございます。
〇天畠大輔君
代読いたします。そもそも、入院時の介助者の付添いは全病院で認められるべき、この機会に周知してくださるようお願い申し上げ、質疑を終わります。