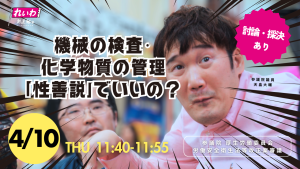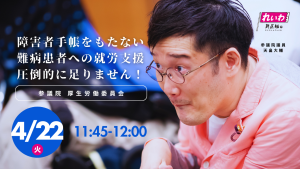2025年4月15日 厚生労働員会質疑「女子中高生 自殺増の分析は社会全体の課題です」
〇天畠大輔君
れいわ新選組の天畠大輔です。政府は「助けて」と言える社会にすべきです。代読お願いします。
4月3日、この厚労委員会の質疑で政府もご答弁されたように、ほとんどの年代、属性で自殺者数が減少する中で、女子中学生と定時制・通信制に通う女子高校生の自殺は増えています。
2023年から2024年の1年間で、女子中学生は80人から99人へ24%増。定時制・通信制の女子高生は66人から81人へ23%増、2022年からの2年間で見ると、47人から81人へ72%も増加しています。自殺には様々な要因が重なるからこそ、ケースごとの丁寧な分析の蓄積が重要だと考えます。
こども家庭庁の令和5年度調査事業「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」では、警察庁の自殺統計原票だけでなく、『子供の自殺が起きたときの背景調査の指針 改訂版』に基づく「基本調査結果」と「詳細調査報告書」の収集と分析が試みられました。しかし、その提供数の少なさなど、調査の限界が述べられています。
文科省に伺います。『子供の自殺が起きたときの背景調査の指針 改訂版』では、基本調査や詳細調査の目的はどのように書かれていますか。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
お答えいたします。委員ご指摘の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」におきましては、自殺または自殺が疑われる死亡事案が生じた際に基本調査や詳細調査を実施することとしておりまして、その調査の目的というものは、まず一つ目に今後の自殺防止に生かすため、二つ目に遺族の事実に向き合いたいなどの希望にお応えするため、そして三つ目が子どもと保護者の事実に向き合いたい等の希望に応えるためとしております。学校及びその設置者は、この背景調査の結果を重んじて主体的に再発防止に取り組むものと考えております。
〇天畠大輔君
代読します。ありがとうございます。子どもの自殺増とその背景分析は社会全体の課題です。今回の法改正では、子どもの自殺防止への学校の責務も明文化されます。今ご答弁いただいたように、背景調査は自殺防止に生かすことが目的なのですから、調査研究にあたり、国が責任を持ってこれらの資料の収集方法やフォーマットの改善などをすべきではないでしょうか。こども家庭庁、文科省の順に、それぞれの今後の施策についてお答えください。
〇副大臣(辻清人君)
こども家庭庁です。お答えします。こども家庭庁では、令和5年6月に取りまとめた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づいて、関係機関が保有する自殺統計や関係資料を集約して、多角的な要因分析を行う調査研究を実施しています。
令和5年度の調査研究では、自殺統計の集計のような従来の手法では把握できなかった自殺者の生前に置かれていた状況などの情報を確認できました。一方で、調査研究への資料提供の可否を提供元が判断できずに結果的に提供されなかった資料があるなど、情報収集に関する課題が明らかになっています。
令和6年度の調査研究では、こうした課題について、例えばですけど、文科省と説明会を共催して、調査研究の目的や資料提供の詳細な方法を説明したり、教育委員会等が資料提供の可否を検討する期間を前回よりも長くするなど、所要の見直しを行いました。
今後も、子どもの自殺の要因分析について効果的な調査を実施できるよう、文部科学省とも連携しながら対応を検討していきたいと考えています。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
お答えいたします。現在の指針におきましては、基本調査や詳細調査における様式などは定めていないため、文部科学省が設置している「児童生徒の自殺防止に関する調査研究協力者会議」におきまして、現在、この基本調査、詳細調査の調査目的に照らした調査項目等について議論をしていただいている。あっ、自殺予防ですね、失礼いたします。「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」というところですね、おいて、現在、基本調査、詳細調査の調査目的に照らした調査項目等についてこの議論をしていただいております。
引き続き、この指針において、現場で活用していただけるような様式や調査項目等を提示できるように議論を重ねてまいりたいと考えております。以上です。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
学校しか知り得ないこともあります。引き続き改善を求めます。代読お願いします。
次に、定時制・通信制に通う女子高校生の自殺が増えたことを踏まえて伺います。全日制と比べて、定時制と通信制、それぞれについてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置状況はどうなっていますか。文科省、お願いいたします。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
文部科学省が実施します、実施するこの補助金を活用したスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの公立高等学校の配置状況としましては、令和5年度実績としてスクールカウンセラーは約79%、スクールソーシャルワーカーは約49%において対応がされているところでございますが、課程別の配置状況というのは現在把握してはおりません。
〇天畠大輔君
代読します。定時制・通信制への配置状況はわからないとのことでした。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは普及してきていますが、子どもたちへのきめ細かな対応を考えるならば、全日制、定時制、通信制、それぞれの配置状況の把握は必須です。統計を取ってはいかがでしょうか。金城政務官、お願いいたします。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの具体の配置については、各教育委員会等の権限と責任のもとで、各高等学校における状況等を踏まえ判断しているものと承知しているところでございます。
現時点におきましては、高等学校の課程別の配置状況について把握しておりませんが、今般の自殺統計に係る定時制や通信制の状況も踏まえ、現在、今後の把握のあり方について検討をしているところでございます。以上でございます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
ありがとうございます。検討を進めてください。待遇改善も必要です。代読お願いします。
スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを定時制・通信制へ配置していくにあたっては、無期雇用の正規職員とすることが重要と考えます。これに対する政府の見解と、正規職員化に向けた取組状況を教えてください。また、正規職員化以外にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの待遇改善に向けた取組があれば、文科省より教えてください。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
お答えいたします。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの採用条件や任用方法につきましては、各教育委員会等の権限と責任のもと、適切に判断されるべきものと承知しております。
そのうえで、現在、文部科学省におきましては、スクールカウンセラー等が常勤の職として求められる職責や担うべき職務のあり方等の検討に資する調査研究を実施しているところでございます。
文部科学省としましては、令和7年度予算におきまして、スクールカウンセラー等の配置充実等に必要な経費として約86億円を計上しているところでありまして、引き続き学校における教育相談体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
配置時間充実だけでなく、無期雇用の正職員化も重要だと思いませんか。金城政務官、お願いします。
〇大臣政務官(金城泰邦君)
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーのこの報酬や日数などいわゆる採用条件につきましては各教育委員会等の権限と責任の下に実情を踏まえて判断されるべきものでありますが、文部科学省としましては、各教育委員会が適切な人材を確保できるように引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
〇天畠大輔君
代読します。次に行きます。
昨年12月の質疑で私は精神科病院での携帯電話やスマートフォンの利用実態調査を求めたところ、今年3月31日付けで、厚労省から都道府県宛てに事務連絡が発出されました。この事務連絡では「可能な限り、携帯電話等を自由に使用できることが望ましい」と明記しました。そのうえで、使用可能な精神科病院に運用上のルールや効果を聞き取り、事例を紹介しています。どうやってトラブルを防ぐか、ルールを作るかということに力点が置かれています。
一方で、この事務連絡に当の患者の声は一つもありません。携帯やスマホを院内で使えるようにすることの目的は、厚労大臣告示130号に定めるように、患者の人権を守るためであることは論をまちません。今後の取組として、精神障がい当事者へのヒアリングを行うべきではないでしょうか。大臣、お答えください。
〇国務大臣(福岡資麿君)
ご指摘の通知につきましては、精神科病院における入院患者の携帯電話やスマートフォンの使用等に関する取組事例等を周知する目的で、本年3月31日付けで、都道府県、指定都市宛てに発出をしたものでございます。
本通知を発出するにあたりましては、入院患者に対して携帯電話等の使用を可能としております複数の精神科病院に対しまして、運用上のルールや携帯電話等の所持、使用による効果または課題等について個別に聞き取りを行い、発出をさせていただいたところでございます。
この通知は、各病院の取組内容等から、参考となる事例を示しながら、各都道府県、指定都市に対し、管下の精神科病院に対して周知を依頼しているものであることから、まずはこの通知の周知を図ってまいりたいと思います。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
大臣、携帯、スマホの利用目的は権利保障にありますよね。お願いします。(発言する者あり)
大臣、携帯、スマホの利用目的は権利保障にありますよね。お答えください。
〇国務大臣(福岡資麿君)
大臣告示で定めております通信の自由にはその具体的な手段までは定めてございませんが、その同告示におきまして、電話機は患者さんが自由に利用できるような場所に設置されている必要があるというふうにしてございます。
今般の通知は、それに加えまして、近年の携帯電話であったりスマートフォンの普及状況等を踏まえ、精神科病院における取組を進めていくために発出しているものということでございます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
そうであれば、当事者にも聞き取りをすべきではないですか。大臣、お願いします。
〇国務大臣(福岡資麿君)
今般、携帯電話等の使用に関する病院からのヒアリングにつきましては、当事者団体の皆様からの病院内で携帯電話等を自由に使用できる、自由に使用できるようにするべきとのご指摘も踏まえ、精神科病院の取組の促進を図るために実施したものでございます。
また、この通知におきましては、患者さん自身が携帯電話等を使用することによりまして、入院中でも患者の人間関係や地域との交流を維持しやすくなり、入院への抵抗感の軽減や、患者さんの安心感の醸成につながると感じる病院が複数あったなど、入院患者さんに対する効果もお示しをさせていただいているところでございます。
こういった通知の周知を図っていきながら、通知発出後の状況もしっかり見ながら、必要に応じて今後の対応については検討してまいりたいと思います。
〇天畠大輔君
当事者への聞き取りを行う余地はあると受け取りました。引き続き求めてまいります。終わります。