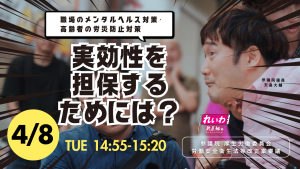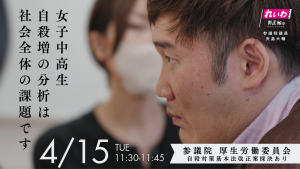2025年4月10日 厚生労働委員会質疑(労働安全衛生法等改正案審議)「機械の検査・化学物質の管理『性善説』でいいの?」
〇天畠大輔君
れいわ新選組の天畠大輔です。検査する側とされる側が同じなのは安全上問題です。代読お願いします。
時間の関係で、質問1と2は飛ばします。厚労省は「審査及び検査における公平性を確保するため」として、製造許可申請の審査及び製造時等検査を行う登録設計審査等機関に関して、法律で3つの要件を課しています。
- 親法人が製造者等でないこと
- 役員の過半数が製造者等で占められていないこと
- 代表権を持つ役員が製造者等の役職員でないこと
です。
しかし、検査機関の役員の半分まで製造者の役職員で構わないなどという組織が、果たして公正で中立的な審査を行うことができるでしょうか。メーカーに対して極めて甘い規定と言わざるを得ません。やはり、大型機械の安全性については公的機関の審査・検査が絶対に必要と考えます。
2024年に開催された検討会の取りまとめには、民間委託を進める一方で、行政機関が、技術の進歩への対応等の必要性も踏まえ、適切に製造許可及び検査を行う能力を維持することが必要と示されています。また、落成検査・変更検査・使用再開検査は引き続き行政職員が担います。さらに、本改正案が成立・施行されても、すぐに100%民間移管になるわけではありません。総合的に考えても、高度な専門性を持つ行政職員の確保は、変わらず喫緊の課題です。
政府は、2008年にこれまで各種の検査業務を担ってきた安全衛生分野の技官の採用を停止したため、労働基準監督官が監督業務と併せて安全衛生業務を担わざるを得ない現状です。結果的に、検査業務に関する専門性の継承が困難となっています。このような状態で、ボイラーや移動式クレーンのような特定機械の安全性が本当に達成できるでしょうか。
それにもかかわらず、政府は、将来的に安全衛生分野の技官をどのように採用・育成していくのか、具体的な方針を示していません。この点は全労働、全労働省労働組合が厳しく指摘しており「安全衛生行政の将来にとって極めて重大なこの課題を脇に置いて検査業務のあり方を議論していること自体、適切でない」と評しています。
安全衛生分野の技官の採用を復活し、労働基準監督官共々、人員を抜本的に増やすべきと考えますが、大臣、いかがですか。
〇国務大臣(福岡資麿君)
クレーン等について現に生じている災害は、玉掛け作業中の事故などクレーン等の取扱方法によるものでございまして、このような災害を防止するためには、作業現場において安全な玉掛け実施など関係法令が遵守されることが重要であることから、労働基準監督署による指導を通じて違反の是正を図る必要があります。
一方で、設計審査であったり製造時等検査に求められる知識・経験が専門高度化していること、十分な知識、経験を持つ民間検査機関が存在することを踏まえますと、設計審査等を民間検査機関が担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることで、より効果的に災害の防止・減少を図ってまいることが必要だと考えております。
また、安全衛生業務に関する専門性を有する職員につきましては、理系の試験区分、つまり、法文系と理工系で採用してございますが、理系の試験区分で採用されました労働基準監督官を中心に中長期的に育成をしているところでございます。これは、安全衛生分野の指導監督業務と、安全衛生に関する技術的な指導等を行う安全衛生業務との関連が相互に増大していることなどから、従前に行っておりました技官の採用から、労働基準監督官の採用に一本化することとしたものでございます。
効果的な指導を行う観点から、引き続き、現在の採用の枠組みの下で安全衛生業務に必要な専門性の確保が図れるように、人材の確保並びに育成に努めてまいりたいと思います。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
安全性の観点から「性善説」は絶対禁物です。代読お願いします。
国交省は、昨年6月、自動車メーカーのスズキ本社に立入検査をしました。型式指定申請時の認証試験における不正行為の疑いでした。不正行為の対象となったのは同社の主力軽自動車の貨物仕様車であり、2014年12月からの3年間で、生産台数2万6023台、販売台数は2万5999台に上っていました。10年もの間不正が見過ごされてきたわけです。同様の不正行為はホンダやマツダでも行われていました。いずれも日本の基幹産業の一翼を担う有力メーカーです。
政府は、本法案の検査精度の更なる民間移管について「民間機関の中には長年にわたりJIS規格の原案作成に携わっている機関もあり、十分な知見を有する」と言いますが、楽観論に流されて監視体制をおろそかにしてはなりません。公的機関による検査体制は断固維持すべきと改めて訴え、次に行きます。
時間の関係で質問4は飛ばします。化学物質による健康障害防止対策の推進について伺います。本法案では、化学物質の譲渡実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける一方で、化学物質の成分名が「営業秘密」である場合に、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名の通知を認めるとしています。代替名の決定は、名称の一部を置き換えまたは削除することで行う方向です。
営業秘密の範囲や非開示が可能な成分を限定するなど国が一定のルールを作るとはいえ、成分名の非開示を決定する主体はメーカー等の譲渡・提供者です。メーカー等が国のルールに基づいて適切な運用を行っているのか、行政は事前に把握していないことになります。働く人の安全を守るための法案において、企業が秘密にする化学物質の名称が行政にすらブラックボックス化する制度設計には疑念を抱きます。
危険性の高い成分まで営業秘密扱いにしていないか、代替名を決定する際に必要以上に各要素の置き換え・削除をしていないか、行政はどのように監督するのでしょうか。法案の説明資料には「EU等の仕組みを参考に」とあります。EUの場合は、営業秘密に該当する化学物質の名称に代替名を使用するには、欧州化学庁、ECHAへの申請・許可が必要です。つまり、化学物質に関する情報を非開示にする際、あらかじめ行政の目が入ります。
営業秘密の保護の必要性がある一方で、人体への影響等の安全性を確保する観点からは、性善説に立つのではなく、行政への申請・許可を前提とした仕組みは検討されなかったのでしょうか。厚労省より短く簡潔にお答えください。
〇政府参考人(井上努君)
代替化学名等の通知について検討を行った専門家検討会におきまして「行政機関への届出を求める必要はないとすべき」と結論を得たことによって、今回の方針で進めさせていただいております。
今回の法案では、有害性の高い物質は代替化学名等の通知を認めないこととしており、代替化学名の通知を認めるのは化学物質の成分名のみ、「人体に及ぼす作用」、「貯蔵または取扱いの注意」、「流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急措置」等、成分名以外の通知事項についてはこれまでどおり記載し、通知を受けた側が化学物質、危険有害性を適切に入手できるように配慮をしております。
また、代替化学名等は事前の行政機関への申請は行いませんが、労働基準監督署が求めた場合には開示義務を課し、適切に設定されていないことを把握した場合には、労働基準監督署において法違反の是正を指導するとともに、重大・悪質な法違反が認められる場合には送検するということも考えております。
このような対応によって、行政への事前申請を求める仕組みはなくとも代替化学名の通知が適切に行われるものと考えております。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
〇天畠大輔君
大臣、せめて届出制を検討すべきではありませんか。
〇政府参考人(井上努君)
繰り返しでございますが、先ほど諸々申し上げた方策を取ることで、行政への事前申請を求める仕組みはなくとも代替化学名の通知が適切に行われると考えております。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
〇天畠大輔君
化学物質の管理についても性善説に立ち過ぎではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
〇国務大臣(福岡資麿君)
今回の仕組みにつきましては、この化学物質の専門家による有識者検討会でご議論いただいた上で、公労使の代表が参加する労政審において取りまとまったものでございます。
重ねてになりますが、有害性の高い化学物質は代替名表示が認められないこと、人体に及ぼす作用などの健康障害を防止するために必要な事項は通知されること、労働基準監督署において法違反の是正を指導すること、重大、悪質な法違反が認められる場合には送検することなどにより、事前審査、許可の仕組みを取らなくても代替名の通知が適切に行われるものというふうに考えておりまして、決して性善説に立ってこういうことをやっているというわけではございません。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
〇天畠大輔君
せめて「検討する」は言ってもらいたかったです。代読お願いします。
代替名を使用した成分に新たな有害性が発見された場合はどうなるのでしょうか。厚労省は「新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には、代替化学名等の通知が認められるものでなくなる」と説明しています。しかし、届出の必要すらない中で有害性が発見された場合に、メーカー等が代替化学名通知を中止するよう行政が速やかに指導できるのでしょうか。厚労省、やはり懸念が残りませんか。
〇政府参考人(井上努君)
代替化学名等を通知する化学物質は、厚生労働省がリスト化をし公表する方針としております。仮に新たな有害性が発見され、危険性、有害性が低い物質と認められなくなった場合には、リストから除かれ、代替化学名等の通知が認められなくなる仕組みといたします。
リストから除かれた場合に速やかに対応できるよう、変更されたリストを直ちに厚生労働省ホームページ等で公開し、化学メーカーを含む関係団体に周知徹底することにより、事業者に対し適切な対応を求めていくと考えております。
〇天畠大輔君
労災を防ぎ、命を守る制度設計を求め、質疑を終わります。
〈反対討論〉
〇天畠大輔君
性善説で労働者の安全は守れません。代読お願いします。
れいわ新選組の天畠大輔です。私は、会派を代表して「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」に対して反対の立場から討論を行います。
反対理由の第1は、本法案があまりに事業者に対する性善説、楽観論に基づく無責任な姿勢に貫かれているからです。特定機械の検査に関しては、定期的性能検査やボイラー、一般クレーンの製造時等検査についてすでに民間移管が進んでいますが、今般の法改正で更に、移動式クレーンも含め、製造許可申請の審査がまとめて民間移管されることになります。今しがたの質疑でも指摘したとおり、民間検査機関は実際には製造者と一体です。検査する側とされる側が同じという仕組みの中で、本当に安全審査ができるはずがありません。
反対理由の第2は、本来安全審査のとりでになるはずの公的機関の審査体制が、労働安全分野の技官の採用停止、労働基準監督官の減員によって無残に切り崩されているからです。ボイラーやクレーンなど大型機械が使われる労働現場では、ひとたび労働災害が発生すると、その被害は甚大です。
2017年2月、橋梁を製造する会社の和歌山工場で、クレーン作業中に倒れた500キロの部材の下敷きになった22歳の若者は、頸椎と脳幹部を損傷し、亡くなりました。残された母親は、事故の真相を知ろうと必死の思いで元同僚の職場に赴き、やっとのことで「作業手順に間違いがあった」という証言を聞き出しました。労働現場から労働災害をなくさなければなりません。そのための第一歩は、生産手段に対する徹底的な安全検査です。
反対理由の第3は、化学物質の成分名が営業秘密である場合には「代替化学名の通知を認める」という点です。人々の命と健康よりも企業利益が優先されるとでも言うのでしょうか。「一定の有害性の低い物質に限る」という条件付ではありますが、当初無害だと思われた化学物質について、後で有害性が発見されるという例は珍しくありません。厚労省は「新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には代替化学名等の通知が認められなくなる」から心配ないと説明しますが、ここでもまた、化学物質使用企業に対する根拠なき「性善説」が色濃く見て取れます。
すべての化学物質について公的機関への申請を義務付け、企業秘密の保護を法的にしっかりと担保すればこのような問題は直ちに解決するのではありませんか。政府はもっと人々の命と健康を守る立場に立つべきだと強く申し上げ、反対討論といたします。