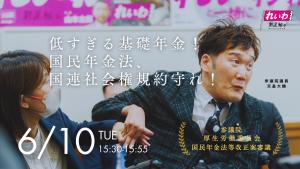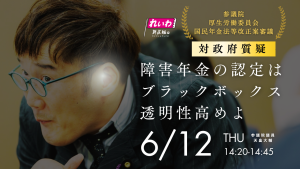2025年6月11日 厚生労働委員会質疑(国民年金法等改正案審議 参考人質疑)「国民年金法等改正案 専門家に聞く」
〇天畠大輔君
代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。参考人の皆様、本日は貴重なお話をありがとうございます。
初めに、伊藤参考人に伺います。被用者保険の適用拡大や在職老齢年金の見直しなど、伊藤参考人は就労促進を重視された提言をなさっています。一方で、障がいや病気、介護など様々な事情で働きたくても働けない方々もおられます。そうした方々にとっては、就労による保障よりも生活そのものを支える年金の安定が重要です。就労可能な方への支援とそうでない方への支え、どのようなバランスが必要とお考えでしょうか。
〇参考人(伊藤仁君)
我々の要望として申し上げています在職老齢年金の話とか、あるいはその適用期間の延ばしていくことの検討という点については、全体的な方向性として年金制度の安定のために必要だというふうに考えてそういうご意見を申し上げているわけでございますけれども、ご指摘のような、実際に働けない方に対するその制度の体系というものは、当然そういうものも考慮してといいますか、そういうことを踏まえてそういう制度設計はすべきであるというふうに考えております。
バランスというのは、我々も正直その全体の、数字的なといいますか、規模感的なことを承知しているわけではないので、基本的な考え方として、ちゃんとそういうところには配慮すべきだという程度のことしか申し上げられませんけれども、やはりそこは区別して考えるべき問題だと思っております。以上です。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
働きたくても働けない人もいます。ありがとうございます。
代読いたします。次に、駒村参考人に伺います。障害年金の不支給増加の問題が報道され、現在、厚労省は調査を実施しております。私は、以前から、障害年金の基準が現代にそぐわない内容を含むこと、医学モデルに偏り過ぎて実際の生活上の困難さが認定上きちんと考慮されていない問題を指摘してきました。しかし、障害年金については議論が進んでいません。
まずは、年金部会で何を議論すべきか整理したうえで専門委員会を立ち上げ、当事者や社会モデルの視点を持った専門家も委員として参画したうえで障害年金の認定基準や認定の仕組みを含めて議論を進めるべきと考えています。駒村参考人のご意見をお聞かせください。
〇参考人(駒村康平君)
ありがとうございます。今回の年金部会では、障害年金に関しては幾つか報告がございましたけれども、そのあり方に関して踏み込んだ改革は行われていないというのはそのとおりであります。
医学モデルに偏っているというのはおっしゃるとおりでして、現行の障害の認定は、診断、検査結果、医学的指数で評価は行われていると。しかしながら、世界的に見ますと、生活機能や社会参加、環境因子という、この生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあり、それで、社会モデルを適用した障害年金の制度もドイツ、スウェーデンなどではすでに反映されているということでございます。
現在の医学モデルだと、障害か障害でないか、二分モデルになりますので、やはりその間があるということで、グラデーションを考えていかなければいけないと私も思っております。
3号の制度もそうですけれども、障害年金についても、年金財政検証とは別に、社会のあり方から、その改革については継続的に、この5年に一遍というような議論ではなくて、継続的に議論する場が必要だと思います。
他方で、障害は、身体、精神、知的、様々な特性がありますし、現行制度からの切替えなど技術的な部分も大変多いので、時間を掛けた慎重な議論も一方では必要だと思っております。以上です。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
社会モデルの観点については私も同感です。年金部会への当事者参画についてはいかがですか。駒村参考人に伺います。
〇参考人(駒村康平君)
年金部会は5年に一度の間隔で、財政的な評価という点でかなり技術的な部分が多くあるのかなと思っております。
障害年金については、少し分けて議論をするという場があってもいいんじゃないかと思いますので、そこにおいて障がいをもたれた当事者の方のお話は聞くべきではないかとは思っています。
これは、私、障害施策いろいろ関わっていますけれども、この社会モデルというのは、障害施策、障害就労、福祉も年金も含めて社会モデルを横断的に考えていく必要があると。その中で、障がいの部分については当事者のお話を聞く場が必要なのかなと思います。以上です。
〇天畠大輔君
代読します。ありがとうございます。引き続き、駒村参考人に伺います。
駒村参考人は、介護や障がい、健康上の理由で就労や保険料納付が困難な人に対して、保険料免除の活用と拡充された年金生活者支援給付金による最低生活保障が必要だと述べておられます。
現在の制度や今回の年金改革案と比較して、駒村参考人のお考えになる最低所得保障型の年金制度とのギャップはどの程度あるとお感じでしょうか。また、こうしたビジョンを実現するには、どのような制度設計や社会的議論が必要と考えていらっしゃいますか。私たちれいわ新選組でも、最低保障年金の具現化に向けて力を入れていきたいと考えております。是非お考えをお聞かせください。
〇参考人(駒村康平君)
今日の議論で厚生年金の適用を880万人まで広げると。私も、基本的には、ほとんどの方を厚生年金、もっと広げると所得、応能負担型の年金に組み込んでいくというのが正しくて、基本的には、1号のような方はなるべく、制度そのものも見直していく、なるべく少ない方がよろしいんではないかと思います。これができれば今回のような調整をしなくてもいいわけですけれども、実際に880万人まで適用するのは時間が掛かるだろうと思います。
ただ、あるべき姿としての、最終的には能力に応じた負担ができるような年金制度を確立すると。そのうえで、未納というものは少し問題ありますけれども、年金が十分でない方については、年金テスト付きの、資力調査のないタイプで年金のテスト付きの高齢者向けの最低所得保障の仕組みを将来的には導入していく必要があるんではないかと思います。
現実には、今回、基礎年金の引上げという形で緊急的に対応したということでございますけれども、さらに、次のステップとしては、先生先ほどお話しした年金生活者支援給付金制度の拡充などを通じて最低保障的な機能を高めていく必要があれば、できれば、それの目指す姿に接近していくんではないかと思います。以上です。
〇天畠大輔君
代読いたします。ありがとうございます。引き続き、駒村参考人に伺います。大変失礼しました。時間ですので、参考人の皆さん、どうもありがとうございました。終わります。