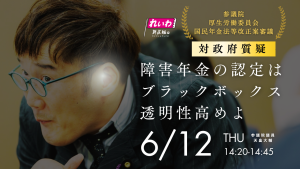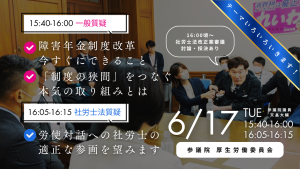2025年6月12日 厚生労働委員会質疑(国民年金法等改正案審議)「対総理 国民年金法等改正案質疑」
〇天畠大輔君
代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。先ほどの福岡大臣への質問に続き、石破総理にも障害年金について伺います。
昨日の参考人質疑において、社会保障審議会・年金部会の委員でもある駒村康平参考人は「現行の障害の認定は医学モデルに偏っている。世界的には生活機能や社会参加、環境因子という生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあり、社会モデルを適用した障害年金の制度もドイツ、スウェーデンなどでは既に反映されている」と述べました。
私は、障害年金の認定基準については、医学モデルと社会モデル、両方の視点のバランスが大変重要と考えていますが、総理のお考えをお聞かせください。
〇内閣総理大臣(石破茂君)
現行の我が国の障害年金は、個人の心身の機能障害に着目する医学モデルか、社会における障壁に着目する社会モデルかと、こういう二者択一ではなく、主治医が作成する診断書に加え、本人や家族が記載する申立書を提出していただくことにより、機能の障害だけではなくて日常生活の状況なども考慮して障害等級の認定を行っていると、このようなことでございます。
障害年金の認定につきましては、昨日、実態把握のための調査報告書が公表され、今後これを踏まえて運用改善を着実に行ってまいりますが、その中では、より客観的かつ公平な認定となるように障害認定審査委員会に福祉職を参画させると、このような運用改善を図ってまいります。
障害認定基準の在り方については、各種のご指摘、今ご紹介がございました諸外国の動向も含めまして、今後、様々なご意見を伺いながら議論を行うべきものだというふうに考えております。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
早く次のステップに進んでください。社会モデルをもっと取り入れてください。代読お願いします。
私は、障害年金の不支給増加問題の背景には、障害認定における構造的な不透明性はもちろんのこと、障がい当事者や社会モデルの視点の欠如も一因と考えています。
認定基準は50年以上前の数値に基づき、いまだに医学モデル中心。当事者の生活実態や社会的困難さは診断書の記述にとどまり、実質的に審査には反映されづらい、これは障害者権利条約が掲げる「社会モデル」の理念からも大きく乖離しています。これは運用の問題だと矮小化することは許されません。これまでも指摘してきましたように、障害年金の認定基準・審査体制に社会モデルの視点をいかに取り入れるか、根本的な見直しを議論するときです。
昨日、駒村参考人も、障害年金を議論する上での社会モデルの重要性、それを当事者の意見を聞きながら議論していく必要性を訴えておりました。また、福岡大臣も、障害年金の論点整理には早期に着手すると答弁していました。私は、意見を聞くだけでなく、障がい当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えます。総理がリーダーシップを発揮し、速やかな会議体の設置をお願いいたします。総理、いかがですか。
〇内閣総理大臣(石破茂君)
ちょっと言葉の定義を間違えますと議論が混乱いたしますので、私なりの理解でございますが、医学モデルというのは、障がいを個人の病気などの医学的要因から生ずるものと、このようにみなす考え方だと承知をいたしております。一方におきまして、社会モデルというのは、障がいを個人の特性だけではなくて社会に起因するものとみなす考え方というような理解の下で答弁をさせていただきたいと存じますが。
障害年金につきましては、厚労省におきまして取りまとめました令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書の不支給事案の分析を踏まえまして、今後、審査書類の丁寧な記載の徹底、認定審査委員会における福祉職などの外部の方の参画など、透明性の確保に向けた運用改善を行うということといたしておるところでございます。
この運用改善は着実に行います。運用改善を着実に行いつつ、障害認定基準の在り方の見直しにつきましては様々なご意見を伺いながら議論を行ってまいる、そのような方針でございます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
曖昧な態度ではなく、具体的な中身を示してください。もっと踏み込んだ答弁をお願いいたします。大臣ではなく総理からもう一度お願いします。
〇内閣総理大臣(石破茂君)
繰り返しの答弁になって恐縮でございます。ご趣旨は、障害認定基準の在り方については社会モデルを更に取り入れることが大切であると、こういうようなご指摘かと承りました。
そういうようなご指摘でございますので、これ、諸外国の動向も踏まえまして、これから先本当に障がいをおもちの方々にとってユニバーサルな社会になっていくように、我々政府として努力をしていかねばならないと思っております。
それが障害者権利条約の趣旨にもかなうものでございますので、ご指摘を踏まえまして政府において真剣に検討し、より良きを目指してまいりたいと存じます。
〇委員長(柘植芳文君)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〇天畠大輔君
最後に、障害年金の公平公正な審査を取り戻すというメッセージを貧困に苦しむ障がい者に是非お願いをいたします。
〇内閣総理大臣(石破茂君)
障害年金につきましては、厚生労働省におきまして、令和6年度の障害年金の認定状況についての報告書の不支給事案等の分析を踏まえておるところでございます。これを踏まえまして、先ほど申し上げましたが、審査書類の丁寧な記載の徹底、認定委員会における福祉職等の外部の方々の参画、透明性の確保に向けた運用改善を行うことといたしております。
精緻な分析というお話を先ほど猪瀬委員との間でさせていただきましたが、障がいをおもちの方々の経済的な状況、今貧困という表現をお使いになりましたが、そのことにつきましても、より精緻な分析をしながら、ユニバーサルな社会の実現に向けて政府として更に取り組んでまいりたいと思っております。ご指摘、ご意見、ありがとうございました。
〇天畠大輔君
よろしくお願いします。終わります。
【反対討論】
〇天畠大輔君
人権を軽視し、庶民を欺く年金議論は許せません。代読お願いします。
私は、れいわ新選組を代表し「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」に反対の立場から討論いたします。
厚労省の調査では、生活が「苦しい」と答える世帯が6割に達しています。老後不安が深まる中で、政府は、年金を「老後の所得保障の柱」と位置付け「実質的価値が保障されている」と述べますが、大うそです。
国民年金のみの受給者は、納付期間25年以上で月平均5.8万円、25年未満では2万円程度しか得られず、年金は生活の「柱」どころか「もたれたら倒れる朽ち木」です。物価が上がっても給付を抑制する「マクロ経済スライド」により年金は実質的に「目減り」しており、この仕組みを見直さない改正案には反対せざるを得ません。
2024年の財政検証では、基礎年金へのマクロ経済スライド適用が影響し、今後の年金水準を著しく低下させる可能性が指摘されました。導入から20年、物価は13%上昇したのに対し、年金は4.4%しか上がらず、実質8.6%減、制度の構造的欠陥が明白です。
政府は「デフレの影響でスライド適用が長期化した」と説明しますが、そのデフレが続いた責任は政府にあり、制度設計の責任も免れません。その結果、急遽「底上げ」が必要になったのです。
しかし、この「底上げ案」は名ばかりです。底上げをもってしても、厚労省は、2050年の基礎年金「満額」を約6.7万円、その所得代替率を33.2%と見込んでいます。それに対し、現在の「満額」は約6.9万円、所得代替率は36.2%です。つまり「底上げ」どころか、下がっているではないですか。
また、精神障がいを理由に障害年金を申請した人に対する不支給認定が1年間で1.9倍以上に急増し、大問題になっています。公平・公正であるべき審査への信頼が大きく揺らいでいます。このような問題の根本には、人権軽視があります。
日本は1979年に社会権規約を批准し、社会保障実現のために最大限の資源活用が義務付けられていますが、防衛費は5年、5年で3兆円増えています。人権の視点が予算に反映されていません。日本国憲法25条「生存権」の理念を政府は真摯に受け止めるべきです。
現行制度の枠内での微修正では生活は改善されません。「厚生年金積立金流用」の批判を受けて、一度は頓挫しかけた法案を与党と野党第一党が共謀して復活させ、マクロ経済スライドの延命に手を貸したのです。
れいわ新選組は、積極財政により最低保障年金を実現し、高齢者も、子どもも、貧困者も、金持ちも、障がい者、障がいがある人もない人も、誰もが「生きていてよかった」と思える社会をつくります。以上、反対討論といたします。